いたや内科クリニックブログ
CLINIC BLOG
-
- いたや内科クリニックブログ
- 食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療
2025.02.02
食中毒は季節にかかわらず、さまざまな要因で発生する健康被害です。しかし予防によってある程度は防ぐことが可能なため、事前に正しい知識を身につけておくことが重要です。この記事では、食中毒の主な原因や予防・対策について解説します。
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|食中毒の原因となる細菌・ウイルス
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|予防と対策
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|食中毒の事故には要注意!
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|食中毒の症状が現れた際におすすめのクリニック
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|まとめ
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|はじめに

食中毒は性別や年齢にかかわらず、誰もが陥る可能性のある健康被害です。
食べ物が傷みやすい夏に発生するイメージが強いですが、細菌・ウイルスによっては冬やその他の季節に発生する可能性もあります。
軽症で済むこともあれば死亡する事例もあり、決して軽視できないものですが、ちょっとした心掛けで予防・対策ができるものでもあります。
この記事では、食中毒の原因となる主な細菌・ウイルス、予防・対策・注意点、飲食店などの食中毒事故について解説します。
また、東中野周辺で食中毒の症状が現れた際におすすめのクリニックも紹介します。
十分に食中毒の予防をしなければいけない環境にいて正しい知識を備えたい方、東中野で食中毒の時に受診できるクリニックをあらかじめ知っておきたい方はぜひご覧ください。
なお、食中毒とは別に消化器系の症状が現れる身近な病気として風邪があります。
風邪全般について詳しく知りたい方は、東中野にある当クリニックの以下ブログをご参照ください。
東中野で風邪症状の治療なら!短期間での回復を目指すクリニック診療
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|食中毒の原因となる細菌・ウイルス
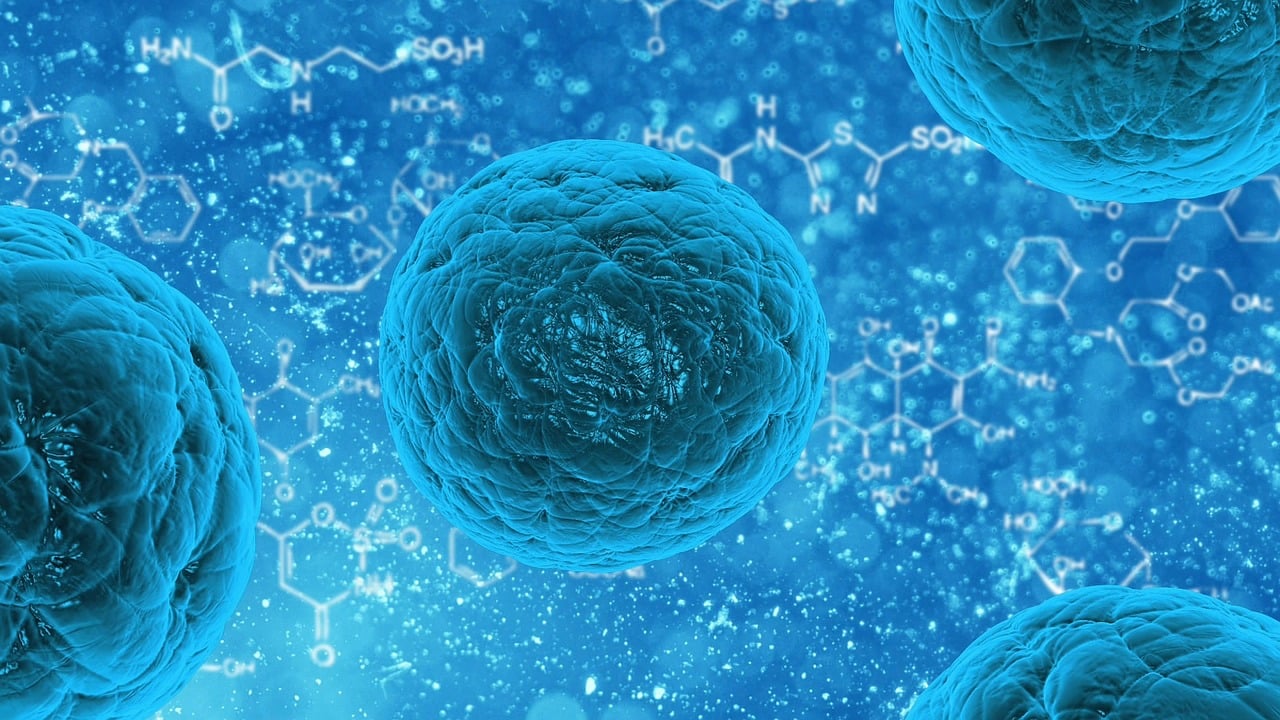
飲食店やその他の食品を扱う施設において食品衛生に関する意識が高まっているため、近年の食中毒による患者数は減少傾向にあります。
それでも、いまだに食中毒の事故件数は常に下がっているということはなく、上下を繰り返している状況です。
そのため食品や料理の提供元だけに頼るのではなく、各々が正しい知識を持って個々での予防・対策をすることも求められます。
ここでは、食中毒の概要を詳しく解説していきます。
分類について
食中毒は、主に細菌性のものとウイルス性のものに分けられます。
他にも寄生虫・化学性・自然毒の食中毒がありますが、特に細菌性、ウイルス性の食中毒の事例は多い傾向にあります。
なお、細菌性はさらに「感染型」「毒素型」の2種類に分類されます。
「感染型」は、細菌が繁殖した食品を摂取し、腸管内でさらに増殖することで食中毒の症状を起こすタイプです。
「毒素型」は、繁殖した細菌から毒素が発生し、その両方を摂取して腸管内で増殖することで食中毒の症状を引き起こします。
いずれも細菌や毒素を摂取することで発症しますが、中には体内に入った後に毒素が産生される「生体内毒素型」に分類される細菌もあります。
食中毒菌は栄養や水分を得て、細菌の好む温度になることで増殖します。
基本的に、人の栄養になるものは細菌の栄養にもなります。
また、細菌が増殖するためには水分が必須となります。
細菌によって適温は異なりますが、10~60℃でほとんどの細菌が活動的になるとされています。
もう一つのウイルス性の食中毒の原因の大半は、ノロウイルスが占めています。
元からウイルスが付着した食品や、感染した人が調理することで食品にウイルスが付着し、それを摂取することで発症します。
特にノロウイルスは少量でも感染力が強く、ウイルスは変異を繰り返すために何度も感染するという特徴があります。
寄生虫としては、サバ・イカ・アジなどに寄生するアニサキスがよく知られています。
寄生虫が含まれる魚などを摂取することで、食中毒を引き起こします。
刺身などの生食に含まれており、寄生虫は十分な加熱や冷凍をすることで死滅するものがほとんどです。
化学性としては、水銀、ヒ素、ヒスタミンなどが挙げられます。
本来は食品に含まれていない有害な化学物質が生産・加工・保存・流通の過程で付着し、それを摂取することで食中毒を引き起こします。
特に、ヒスタミンによる食中毒が多い傾向にあります。
自然毒としては、動物性のフグ毒や貝毒、植物性の毒キノコやジャガイモの芽などが挙げられます。
常に毒があるわけではなく、特定の時期にのみ毒を産生するもの、餌から毒を蓄積するものもあるので、そういった食材を自分で調理をする際は正しい知識が欠かせません。
食中毒による症状
食中毒になると、嘔吐、腹痛、下痢といった急性の胃腸障害がみられるようになります。
場合によっては発熱することもあります。
下痢や嘔吐によって食中毒の原因となる細菌やウイルスを排出して回復に向かい、数日〜2週間程度で落ち着くことが多いですが、重症化して死亡する事例もあります。
また、症状が長く続く場合は、脱水症状にも注意しなければなりません。
なお、具体的な症状は細菌・ウイルスによっても異なるため、詳細については次の項目で詳しく紹介します。
こちらの厚生労働省のサイトでは、さまざまな細菌に関する資料がまとめられていました。
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|予防と対策

ここでは、代表的な食中毒の原因と、それぞれの予防・対策について解説します。
サルモネラ
鶏卵とその加工品、牛レバー刺し・鶏肉、魚などが原因となる細菌で、それらを食べてから6~48時間で激しい腹痛や嘔吐、下痢、発熱といった症状が現れます。
卵、肉、魚介類は新鮮なものを購入する、肉・卵は75℃以上で1分以上加熱する、調理後の器具や手はしっかり洗浄・消毒することが予防法となります。
腸炎ビブリオ
刺身・寿司・魚介加工品といった魚介類全般が原因となる細菌で、食後8~24時間で激しい腹痛、下痢、発熱、嘔吐といった症状が現れます。
調理前にしっかり洗って菌を落とす、調理後の器具や手はしっかり洗浄・消毒する、60℃以上で10分以上加熱する、使うまでに少しでも時間が空く場合はすぐに冷蔵庫に4℃以下で保存するといったことが予防法となります。
O-157(腸管出血性大腸菌)
原因となる食品は様々で、これまで、牛肉とその加工品、サラダ、白菜漬け、井戸水などから発症した事例があります。
潜伏期間が平均4~8日と長く、腹痛、下痢、発熱、嘔吐といった症状のほか、鮮血混じりの血便や血性下痢になることもあり、溶血性尿毒症で死亡する例もあります。
調理後の器具や手はしっかり洗浄・消毒(熱湯や塩素系消毒剤)する、肉は75℃以上で1分以上加熱する、生野菜はしっかり洗う、水道管直結以外の水は飲用可能な水であるか確認することが予防になります。
カンピロバクター
鶏肉、飲料水、生野菜が原因となる細菌で、食後1~7日で下痢、発熱、おう吐、腹痛、筋肉痛、血便、倦怠感、頭痛といった症状を引き起こすほか、数週間後に手足、顔面のまひが現れる症例もあります。
鶏肉や鶏レバーの生食を避ける、井戸水や湧き水は飲まない、調理前にしっかり洗って菌を落とす、調理後の器具や手はしっかり洗浄・消毒する、生肉と他の食品を接触させない、肉は65℃以上で数分は加熱するということが予防になります。
黄色ブドウ球菌
乳製品、卵製品、畜産製品、穀類、魚肉練製品、和洋生菓子などが原因となる細菌で、食後まもなく1~3時間で吐き気、嘔吐、腹痛、下痢といった症状が現れます。
発熱はみられません。
人や動物が保有している菌であるため、食品に触れなければいけない場合はしっかり洗浄する、怪我をしている場合は調理しない、髪の毛やつばが入らない格好をするといったことが予防になります。
加熱調理をすると菌自体は殺菌されますが、菌の出した毒素は無毒化されづらいるため、上記の対策をして菌を付着させないことが重要です。
食品を10℃以下で保存して菌を増殖させないことも効果的です。
ウェルシュ菌
酸素が少ないと増えやすいという特徴があるため、カレーやシチュー、スープ、魚の煮つけや野菜の煮物といった煮込み料理が原因となることが多い細菌です。
6〜18時間で腹痛や下痢(下腹部の張りを伴うこともある)といった症状を引き起こします。食中毒の中では症状が軽度な傾向にあります。
加熱調理後は保存せずすぐに食べる、どうしても保存する場合は小分けにして冷凍することが予防になります。
ボツリヌス菌
缶詰・瓶詰・真空パック食品・いずしといった長期間保存されることが多い自家製の食品が原因となる細菌ですが、蜂蜜やコーンシロップが乳児ボツリヌス症の原因となった事例もあります。
海外では、ハム・ソーセージが原因となった事例もあります。
8~36時間で吐き気、嘔吐、筋力低下、脱力感、便秘のほか、視力障害や発声困難、呼吸困難、ものを飲み込みづらいといった神経症状が現れる場合もあります。
容器が膨張しているものは破棄する、調理時の十分な洗浄と加熱(120℃、4分間以上の加熱で死滅)、保存の際は3℃未満で冷蔵もしくは-18℃以下で冷凍する、1歳未満の乳児に蜂蜜は与えないといいうことが予防になります。
ノロウイルス
カキやハマグリといった二枚貝、感染者の糞便や嘔吐物への接触による二次感染が原因で感染します。
年間を通して感染する可能性はありますが、特に冬の時期に顕著でとなります。
潜伏期間は1〜3日で、発症すると吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱といった症状が現れますが、数日で治ることが多いです。
二枚貝は85℃~90℃、90秒間以上加熱する、精製食品はしっかり洗う、調理や食事の前は入念な手洗いをする、感染者の糞便や嘔吐物を処理する場合はビニール手袋やマスクをつけて完了後は確実に洗浄・消毒をするなどが予防となります。
A型肝炎ウイルス
国内での感染源ははっきりしていないものの、加熱処理が不十分な魚介類や井戸水、二枚貝などが関係している可能性が示唆されています。
海外では、レタスや冷凍ラズベリーなどを感染源とする集団感染とみられる事例が発生しています。
潜伏時間は2~7週間とかなり長く、38℃以上の発熱、倦怠感、食欲不振、おう吐といった症状のほか、黄疸や肝腫大といった症状が出る場合もあります。
なお、幼児においては症状が軽症もしくは無症状であることが多く、高年齢で免疫力が低下していると重症化しやすい傾向にあります。
調理時や生の魚介類に触れた際はしっかりと手洗い・消毒をおこなうこと、生の魚介類を調理した器具をそのまま他の食材に使わない、十分に加熱する、A型肝炎が流行している地域の生水・生物は避ける、ワクチン接種をするといったことが予防になります。
E型肝炎ウイルス
国内では、ブタ、イノシシ、シカの肉や内臓の生食が原因と考えられる事例があるほか、水が感染経路と考えられています。
感染しても無症状であることも多いですが、潜伏期間3~8週間で発熱、吐き気、腹痛や黄疸、肝腫大といった症状が出る場合もあります。
妊婦や高齢者に関しては重症化することもあります。
ブタ、イノシシ、シカの食肉時は中心部まで火が通るように十分に加熱し、生食はしない、E型肝炎が流行している地域の生水・生物は避けるといったことが予防になります。
アニサキス
サバ、サンマ、アジ、カツオ、サケ、スルメイカに宿る寄生虫で、生鮮魚介類を生食して体内に入ると、アニサキスの幼虫が胃壁や腸壁に刺入し、食中毒を引き起こします。
食後数時間~十数時間で発症し、みぞおち部分の激しい痛みや吐き気、嘔吐といった症状が現れます。
数日すると激しい下腹部痛や腹膜炎症状が出ることもありますが、死亡例は確認されていません。
鮮魚を一尾で購入する場合は、より新鮮なものを選び、氷や冷却剤で十分に冷やして持ち帰り、帰宅後はすぐに内臓を取り除くといった対応が重要です。
また、魚の内臓を生で食べるのはやめましょう。
農林水産省のこちらのページでは、子供の食中毒についてまとめられていたので、お子様がいる方は合わせてご覧ください。
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|食中毒の事故には要注意!
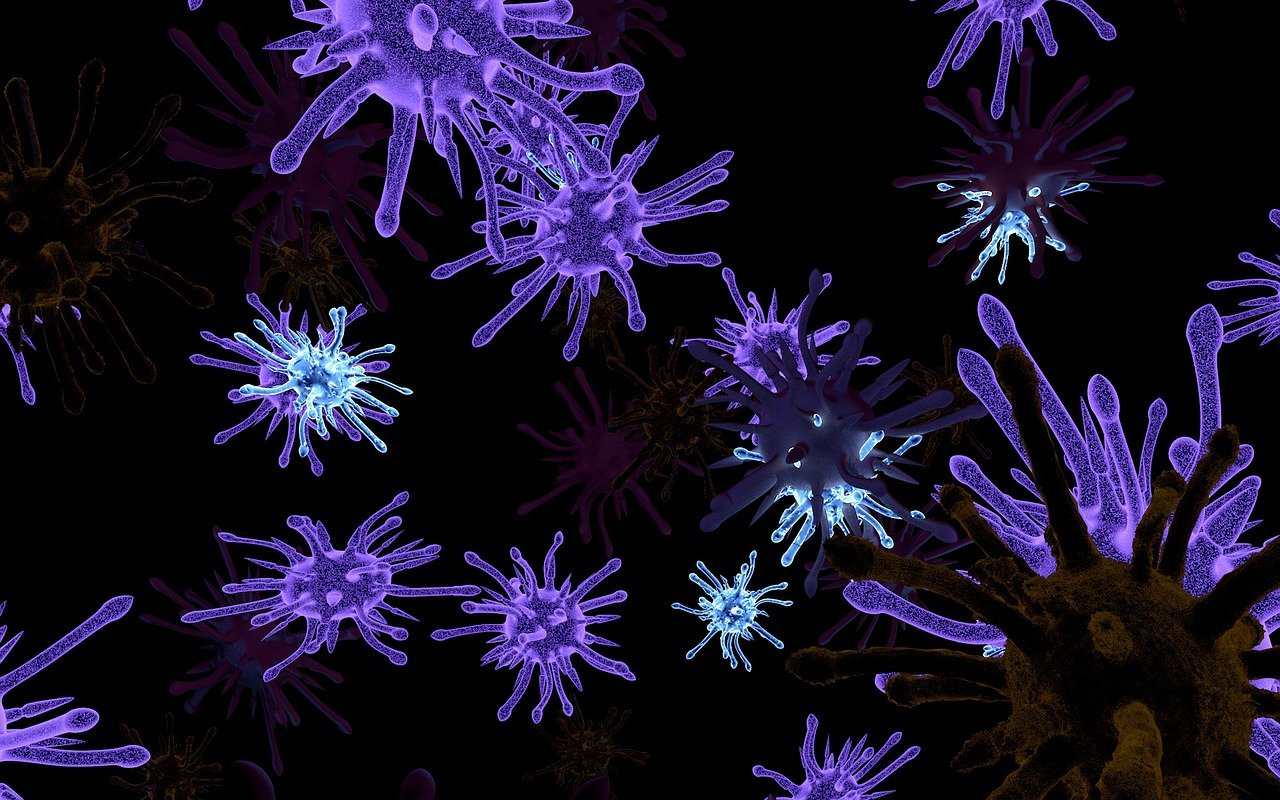
飲食店や食品を扱う店、学校給食などで食中毒事故を起こしてしまうと、行政指導や処分、賠償などが発生する可能性があります。
事故の60%は飲食店で発生していると言われており、営業停止処分・営業許可取り消しが下される場合もあります。
そこまでの処分がなかったとしても、有名な店であればあるほどニュースなどでも取り上げられるため、大きく信頼を失うことになります。
実際にこれまで食中毒事故を起こした店が、今もなお語り継がれているのをご存知の方もいるのではないでしょうか。
食中毒予防の三原則として、「つけない」「増やさない」「なくす」を守ることが重要とされています。
「つけない」とは、菌やウイルスをつけないということです。
人の手や調理器具を介して菌やウイルスが付着して食中毒を引き起こす場合があるので、手洗いや調理器具の使用目的による使い分け、使用後の洗浄と消毒、食材に素手で直接触れない、体調不良者の調理は避けるなどの対策が重要です。
「増やさない」とは、菌やウイルスがついてしまったとしても増やさないということです。
中には少ない量で食中毒を引き起こすものもありますが、量が増えなければ食中毒に至らない場合もあります。
そのため、調理後は時間を置かずに食べてもらう、低温で保存するなどの温度管理が重要です。
最後の「なくす」は、加熱処理によって菌やウイルスを死滅させることです。
多くの菌やウイルスは加熱することで死滅します。
加熱したとしても不十分だと食中毒が起こる可能性があるため、中心部まで十分に加熱処理することが重要です。
客などの申告によって食中毒が疑われる場合は、保健所による立ち入り検査がおこなわれることもあります。
食品を取り扱う店などを経営している場合は、日頃から食中毒予防の三原則を守ることを徹底し、従業員にも徹底しましょう。
厚生労働省では、食中毒事故の予防・対策をするため、食品等事業者や集団給食施設における衛生管理に関するガイドラインを提供しています。
詳細については以下をご参照ください。
同じく厚生労働省のこちらのページでは、過去の食中毒発生事例が掲載されていました。
安心の診療|食中毒の症状が現れた際におすすめの東中野のクリニック

もし食中毒の症状が現れた際におすすめの、東中野やその周辺のクリニックを紹介します。
中野ひだまりクリニック
内科・消化器内科・循環器内科・外科と幅広い診療科目に対応可能なクリニックです。
アレルギー外来や漢方外来、各種健康診断や予防接種、自費診療にも対応しています。
予約はホームページ上からでき、事前問診と保険証の登録が必要となっています。
登録ができない場合も電話での受付が可能です。
内科・消化器内科のどちらもあるので、食中毒のようだけど実際どこを受診したらわからないという時にもおすすめです。
外来の診療時間は木曜を除く月〜日曜日までが9:00~12:30、14:00~20:00、木曜日は休診(訪問診療)となっていて祝日の状況はホームページ上で確認する必要があります。
なお14:00~16:30(土曜は17:00迄)の間は予約での診察のみ可能な時間帯となっている他、第1、3日曜は診療時間が9:00〜17:00となっています。
夜は20:00まで、休日も診療しているので仕事がある人でも比較的行きやすいでしょう。
JR総武線、大江戸線の東中野駅から徒歩4分、東京メトロ東西線の落合駅からも徒歩4分の場所に位置するクリニックです。
東中野クリニック
内科・神経内科・老年内科を診療科目とするクリニックです。
訪問診療に対応しているほか、英語にも対応できるという特徴があります。
診療時間は、平日が8:00~13:00と15:00~19:00、土曜日が8:00~13:00のみとなっています。日祝は休診です。
JR総武線の東中野駅西口すぐそばにあり、地下鉄大江戸線の東中野駅から徒歩1分、地下鉄東西線の落合駅からも徒歩7分の場所にあります。
東中野 セント・アンジェラクリニック
内科・循環器内科・呼吸器内科を診療科目とするクリニックで、オンライン診療にも対応しています。
また、漢方やサプリメントを使った治療や、ワクチンなどの予防医療の相談、健康・美容のための食事・レシピの提案や試食会も実施されています。
美容系の自由診療、花粉症の舌下免疫療法も対応可能です。
新型コロナに関しては、さまざまな症状が見られる後遺症の外来にも対応しています。
診療時間は平日の月〜金曜日まで9:00~12:30と15:00~18:00、木・土は9:00~12:30のみ、日・祝日が休診となっています。
JR東中野駅東口から徒歩6分、東京メトロ落合駅3番出口から徒歩4分の場所に位置します。
関東バス(百01)の「東中野区民活動センター」バス停を利用した場合は、そこから徒歩0分です。
なお、こちらのクリニックでも食中毒について詳しく紹介されたブログが掲載されていました。
おおくら内科
内科・消化器内科に対応している病院なので食中毒の診察が可能です。
胃カメラ・ピロリ菌などの検査や各種予防接種、健康診断、花粉症の舌下免疫療法にも対応しています。
発熱・風邪症状がある場合は事前の電話連絡が必須で、来院時はマスクの着用が必須となります。
診療時間は、水曜日を除く平日が9:30~12:30と14:00〜17:30で、土曜日は9:30~12:30の午前中のみ対応しています。水日祝は休診です。
JR東中野駅前の商業施設「ユニゾンモール」内にあるため、JR東中野駅からは徒歩1分、地下鉄大江戸線からも徒歩4分の場所にあります。
上高田クリニック
内科・循環器内科・外科・血管外科を診療科目とするクリニックで、下肢静脈瘤専門外来がある点が特徴です。
他にも花粉症・アレルギー、禁煙外来、睡眠時無呼吸症候群、各種自費診療、高濃度ビタミンC点滴など幅広く対応しています。
10月から新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンの予防注射も開始されており、同時接種も可能となっていました。
なお、このクリニックで実施されている「デラックスニンニク注射」は、食中毒や重金属中毒などへのデトックス効果もあるとされています。
診療時間は、水曜日を除く平日が9:00〜12:30と15:00〜18:30、土曜日は9:00〜12:30のみとなっています。水・日・祝が休診です。
予約優先制となっていて、ホームページ上からアカウント登録するとWeb予約もできます。
東京メトロ東西線の落合駅1出口から徒歩7分、JR東中野駅西口から徒歩10分、西武新宿線中井駅から徒歩10分、西武新宿線新井薬師駅南口から徒歩12分の場所に位置するクリニックです。
当院について
もちろん当院「いたや内科クリニック」でも食中毒が疑われる症状が現れた際の検査・診断が可能です。
なお当院は高血圧、糖尿病といった生活習慣病の診察もおこなっており、発熱等の風邪の諸症状がある方とは診断時間を分けている点にはあらかじめご注意ください。
主な診療科目は、内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、アレルギー内科、予防接種、生活習慣病、睡眠時無呼吸症候群、自費診療、往診応需です。
JR総武線東中野駅西口から、都営大江戸線東中野駅A2出口からそれぞれ徒歩2分という電車でのアクセスも便利な場所に位置します。
診療時間は、平日の月〜金曜日が9:00〜12:00と14:00〜18:00、土曜日は9:00〜14:00まで途中休憩なしで診療しています。水曜、日曜、祝日は休診です。
発熱外来に関しては平日(月、火、木、金)は11:00〜12:00、15:30-17:00、土曜日は10:30〜12:30での来院をお願いしてます。また電話での完全予約制となっています。
その他のクリニックをお探しの方は、以下のようなサイトも参考にしてみてください。
中野区、食中毒のクリニック・病院 /Doctors File
東中野駅周辺の食中毒を診察する病院・クリニック /caloo
東中野駅周辺のウエルシュ菌食中毒を診察する病院・クリニック /caloo
食中毒に関連する診療科の中野区の病院・クリニック /MEDLEY
食中毒の原因と対策を徹底解説!東中野のクリニックで安心の診療|まとめ

最後にこの記事をまとめます。
- 食中毒は細菌やウイルスが主な原因
- 食中毒の予防・対策には正しい知識が必須
- 食中毒予防の三原則は「つけない」「増やさない」「なくす」
- 東中野には食中毒の診察が可能なクリニックがある
食中毒については、こちらのサイトでもまとめられていました。
東中野で駅近くの病院をお探しなら、「いたや内科」
東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階
Googleマップで見る

 クリニック紹介
クリニック紹介
 診療のご案内
診療のご案内
 いたや内科クリニックブログ
いたや内科クリニックブログ


 03-3366-3300
03-3366-3300