いたや内科クリニックブログ
CLINIC BLOG
-
- いたや内科クリニックブログ
- CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向
2025.04.12
近年「CPAP」はメディアなどでも取り上げられており、睡眠時無呼吸症候群でなくてもなんとなく知っている人が多いのではないでしょうか。この記事では、睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)の治療法の一つ「CPAP」のメカニズムや効果、副作用、研究動向について紹介していきます。
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの基本的なメカニズム
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの効果と臨床研究
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの副作用やリスク
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの副作用やリスク
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|まとめ
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|はじめに

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりして体の低酸素状態が発生する疾患です。
その治療法はいくつかありますが、欧米や日本国内で広く普及しているものとしてCPAP(持続陽圧呼吸療法)があります。
CPAPは、専用の装置からホースやマスクを介して処方された空気を気道に送り、気道が塞がらないようにする治療法で、睡眠中の無呼吸やいびきを軽減することができます。
この記事では、CPAPのメカニズムや効果、副作用、研究動向について紹介します。
睡眠時無呼吸症候群が疑われている方、不安なのでこれから医療機関を受診しようと思っているという方はぜひご覧ください。
CPAPについては、あわせて以下記事もご参照ください。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法!CPAP療法について解説します
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの基本的なメカニズム

CPAP(シーパップ)は、「Continuous Positive Airway Pressure」の略で、睡眠中に気道へ持続的な陽圧を加え、閉塞しやすい上気道を常に開いた状態に保つ治療法です。
専用のマスク(鼻マスクや鼻口マスク)とホースを介して小型の送風機から空気を送り込み、咽頭の軟部組織が睡眠中に潰れないよう、まるで「空気の添え木」のように機能します。
元来は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の治療として開発されたものの、陽圧による呼気終末圧の維持によって呼吸仕事量を軽減できるため、心不全による急性肺水腫など一部の呼吸不全の補助にも応用されています。
CPAPは、咽頭内圧を上昇させることで舌根沈下や軟口蓋の落下による気道閉塞を防ぎます。
さらに、陽圧換気により終末呼気陽圧(PEEP)が維持され、肺胞の虚脱(無気肺)を防いで、換気血流比の改善や酸素化向上にも効果が期待できます。
【参考】
Continuous positive airway pressure
Cardiovascular outcomes of continuous positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの効果と臨床研究
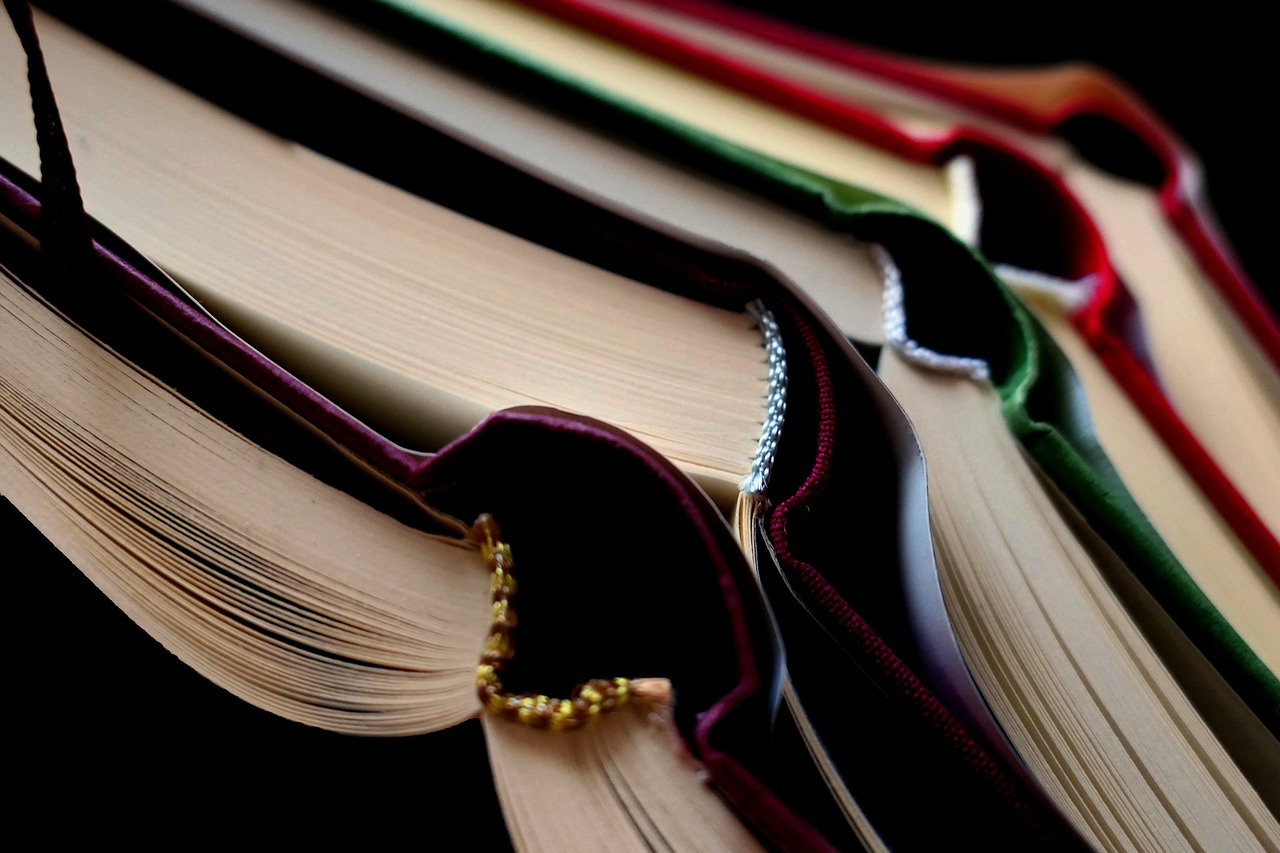
上記で述べたとおり、CPAP療法はOSAの第一選択治療であり、その有効性は多数の研究で実証されています。
例えば、CPAPの使用によって日中の過度の眠気が軽減し生活の質(QOL)が向上することが報告されています。
また、無呼吸低呼吸指数(AHI)など客観指標もほぼ正常化し、ある大規模試験では、AHIが治療前の平均29回/時から治療中は3.7回/時まで低下したというデータもあります。
ランダム化比較試験でも、CPAP使用群はプラセボ群に比べ日中の眠気(エプワース眠気尺度スコア)の有意な改善が繰り返し示されています。
さらに、CPAP継続使用により血圧の数mmHg低下や肺高血圧の改善がみられ、高血圧や耐糖能異常の是正につながる可能性も報告されています。
CPAP治療により、血管内皮機能の改善やインスリン感受性の向上が確認されているのが実情です。
一方で、CPAPが心血管イベントや死亡率を低減するかについてはいまだに議論があります。
OSAと心血管疾患を併発した患者2700人超を対象とした国際多施設RCT(SAVE試験)では、約3.7年の追跡期間において、CPAP併用群と非併用群で主要な心血管イベント(心血管死、心筋梗塞、脳卒中など)の発生率に有意差が認められませんでした。
ただし、同試験の対象患者は元々日中の眠気が軽度であり、CPAP平均使用時間も3.3時間/夜と短かったことから、対象として適切ではなかったことが一因とも言えます。
CPAPを毎晩4時間以上使用できている患者の観察結果においては、未使用患者に比べて心血管合併症や死亡リスクが有意に低下するとの報告もあり、十分な使用時間(アドヒアランス)が治療効果の鍵とみられています。
【参考】
CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|CPAPの副作用やリスク

CPAPは非侵襲的な治療で重篤な合併症はまれですが、マスク装着や陽圧送気に伴う不快症状がしばしばみられます。
それが原因となって、治療継続が困難になるケースも少なくありません。
主な副作用や使用上のリスクとしては、以下のような点があげられます。
鼻・口腔内の乾燥:持続気流により鼻粘膜が乾燥し、鼻づまり、鼻漏、口渇、鼻出血など
マスクによる皮膚刺激:マスクの締め付けによる顔面の発赤や圧痕、皮膚が擦れる事による痛み・かゆみ
装着への抵抗感・睡眠の妨げ:器具への閉塞感や機械音、就寝時の違和感からCPAPを敬遠することにより、患者の3割以上はCPAPを十分に継続利用できていない
稀な合併症:空気嚥下による腹部膨満や鼓腸、マスクをしたままの嘔吐による誤嚥のリスク
なお、CPAP装置そのものに起因するリスクが指摘された例もあります。
2021年には、あるメーカー製のCPAPに内蔵された防音フォーム材が劣化し、有害な微粒子や化学物質が発生する恐れがあるとして約1500万台にも及ぶ大規模リコールが実施されました。
この問題以降、各社で素材選定の見直しや設計改善が図られており、安全性の向上に向けた技術改良が進められています。
【参考】
Recalled Philips Ventilators, BiPAP Machines, and CPAP Machines
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|最新の研究動向と改良技術

近年、CPAP療法の効果をさらに高めるための研究や技術革新が進んでいます。
特に焦点となっているのが、アドヒアランス(継続使用率)の向上です。
遠隔医療(テレヘルス)を活用したCPAP患者支援は有望なアプローチで、遠隔モニタリングにより患者の使用状況を把握しフォローアップを行うことで、CPAPの使用時間と治療効果(症状の改善、疾患重症度の軽減)を向上させることが実証されています。
実際、遠隔モニタリング導入群ではCPAPの使用率が有意に高まり、副作用の減少やQOLの向上につながったとの報告もあります。
このような遠隔技術と教育・行動療法を組み合わせた包括的支援モデルが提唱されており、CPAP療法の効果最大化に寄与すると期待されている状況です。
CPAPデバイス自体の改良も進められています。
マスクの快適性向上は永続的な課題であり、近年は、より装着感の良い新しいCPAP装置の開発例も報告されています。
例えば米国で開発中の「VortexPAP」という装置は、渦流(ボルテックス)気流技術を利用し、気道に必要な陽圧を維持しつつマスク構造を極力簡素化することで、装着時の不快感を軽減することを目指しています。
予備的な臨床テストでは、従来機と同等の気道陽圧を提供しながら顔への接触面積が小さいミニマルデザインのマスクによって「より快適に着用できる」との被験者評価が得られています。
また、従来の汎用マスクではフィット不良に悩む患者向けに、顔面形状を精密に計測してからオーダーメイドの3Dプリンター製マスクを作成する試みも行われています。
30名のOSA患者を対象としたパイロット研究では、このカスタムマスクによりマスク関連の副作用が減少し、CPAPの平均使用時間が従来マスク時の2.4時間/夜から3.8時間/夜へと改善しました。
使用夜数の向上(63%→86%)や満足度の改善も報告されており、個別適合マスクは、従来マスクで十分に適応できない患者に対する有効な対策となる可能性が示されています。
さらに、自動調節式CPAP(APAP)の普及も技術進歩の一つです。
APAPは、内蔵センサーで睡眠中の気道状態をリアルタイムに検知し、必要最小限の圧力を自動で供給することで平均圧を下げ患者の負担を軽減します。
複数の臨床研究を分析した結果、APAPと固定圧CPAPの治療成績(低酸素の改善や日中の症状改善効果)に有意差はなく、いずれも同等の有効性を示すとの報告がされています。
適切な圧力の自動調節により不要な高圧曝露を避けられるため、一部の患者ではAPAPの方が副作用(胃の張りなど)の軽減につながるとの知見もあります。
また、近年のCPAP装置は通信機能を備え、クラウド経由で治療データを共有・解析できるスマートCPAPへと進化しつつあります。
これにより、医療者による遠隔の設定調整や患者へのフィードバックが可能となり、よりきめ細かな個別最適化治療が実現しつつあると言えます。
以上のように、CPAP療法は確立されたOSA治療法であると同時に、副作用低減や継続率向上を目指した改良が続けられています。
最新の研究は、デバイス技術と患者支援の両面からCPAPの効果を高める方向に進んでおり、今後もより快適で効果的なCPAP療法の実現が期待されています。
【参考】
APAP vs CPAP
UC researchers develop new CPAP device
CPAP(持続陽圧呼吸療法)の最新研究動向|まとめ
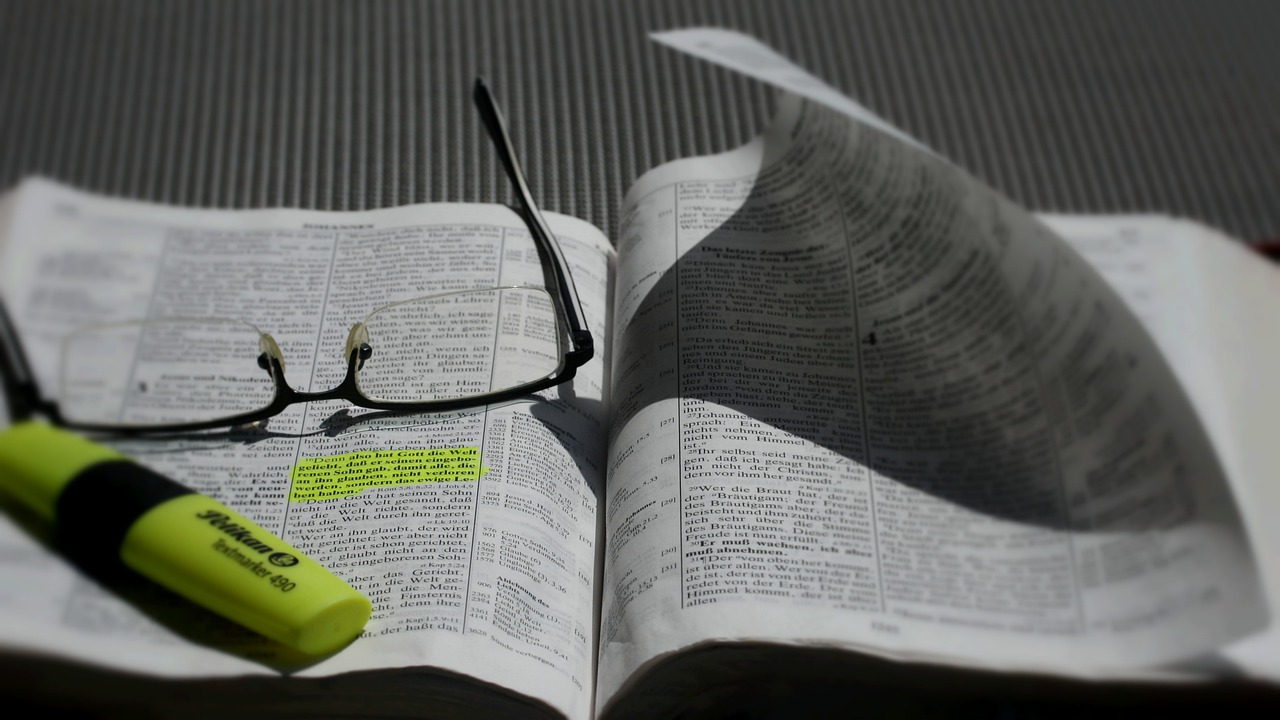
最後にこの記事をまとめます。
- CPAPは睡眠時無呼吸症候群の治療として効果的
- CPAPにより眠気改善や血圧低下などの効果がある
- 心血管リスク低下には継続使用時間が重要とされる
- 鼻や皮膚の不快感などで継続困難となる場合がある
- テレヘルスや新型マスクでアドヒアランス改善が進む
中野区東中野にある当院「いたや内科クリニック」では、以上のような研究の動向を追いながら日々診断・治療をおこなっています。
自分が睡眠時無呼吸症候群なのではないかと気になっている方は、こちらのセルフチェックなどをお試しください。
ただし決して自己判断だけでは終わらせず、不安な方は治療お可能な医療機関の受診をおすすめします。
東中野で駅近くの病院をお探しなら、「いたや内科」
東京都中野区東中野3-8-9 東中野医療ビル2階
Googleマップで見る

 クリニック紹介
クリニック紹介
 診療のご案内
診療のご案内
 いたや内科クリニックブログ
いたや内科クリニックブログ


 03-3366-3300
03-3366-3300