東京都中野区の東中野駅周辺で狭心症にお悩みの方へ
-
- 診療のご案内
- 東京都中野区の東中野駅周辺の呼吸器内科
- 東京都中野区の東中野駅周辺で狭心症にお悩みの方へ
東京都中野区の東中野駅周辺で狭心症にお悩みの方へ
どんな病気?
狭心症とは、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を供給する冠動脈の血流が一時的に減少または遮断されることで、胸部や上腹部に圧迫感や痛み、息切れ等を引き起こす病気です。狭心症の主なタイプとして、「安定狭心症(労作性狭心症)」「冠攣縮性狭心症」「不安定狭心症(急性冠症候群を含む)」があります。
労作性狭心症では、階段や坂道、寒冷・ストレス・食後など、心臓に対する酸素要求が増す場面で発作が起きやすく、通常数分以内で安静または硝酸薬で軽減します。対して、冠攣縮性狭心症では冠動脈がけいれん(攣縮)を起こし、安静時や夜間に発作が起きることがあり、典型的な“労作”の誘因がなくても症状が出る点が特徴です。また、不安定狭心症では発作が頻回・増悪・持続時間が長くなることで心筋梗塞に移行するリスクが高まります。
近年では、明らかに冠動脈に明瞭な狭窄を認めないにもかかわらず狭心症様症状を呈する「冠微小血管機能異常(CMD:Coronary Microvascular Dysfunction)」や「非閉塞性冠動脈疾患(INOCA:Ischaemia with Non-Obstructive Coronary Arteries)」の概念も重要視され、従来の“狭くなった大きな血管”だけでなく“血管機能の異常”という視点も診療に反映されています。
発作の典型例では、みぞおち付近〜胸部中央に「締め付けられるような胸痛・圧迫感」があり、冷や汗・吐き気・息苦しさを伴うこともあります。痛みが10〜15分以上続いたり、安静にしても改善しない・左腕・肩・首・あご・背中に放散痛がある・ニトログリセリンで改善しない、という場合は心筋梗塞の可能性もあるため早めの受診が推奨されます。
診断方法
診断は多角的に行われ、以下のような検査・評価が組み合わされます。
・問診・身体所見:胸痛の性状、発作を誘発した状況(運動・寒冷・食後・ストレス)、持続時間、改善・悪化要因、既往歴(心筋梗塞・狭心症・心血管疾患)などを丁寧に聴取します。
・安静時心電図:発作時や発作間欠期に異常(ST下降・T波変化)を認めることがありますが、正常であっても狭心症を除外できません。
・負荷試験(運動負荷心電図など):心筋への血流が不足する状況を再現して、それに伴う心電図変化・症状誘発を観察します。これは特に労作性狭心症の診断に有用です。
・心筋虚血を調べる画像検査:心筋シンチグラフィ・負荷心エコー・冠血流予備能(FFR/iFR)などで、どの部分の血流低下があるか可視化します。
・冠動脈CT(非侵襲的):冠動脈の狭窄・プラークの存在、有無を調べるための検査で、侵襲的検査前のスクリーニングとして用いられます。
・冠動脈造影(カテーテル検査):狭窄部位・狭窄率・血流制限の有無を直接評価。必要に応じ、血管内治療(ステント留置・バイパス術)を検討します。
・攣縮性狭心症や微小血管狭心症が疑われる場合には、造影時に薬剤負荷(アセチルコリンなど)による冠攣縮誘発試験や血管反応検査が併用されることがあります。
また、併存する高血圧・脂質異常・糖尿病・腎機能障害・喫煙・肥満といった冠危険因子も同時に評価し、狭心症の背景・予後リスクを総合的に判断します。
治療方法
治療の目的は「症状の軽減/発作の予防」「心筋梗塞・心不全など重篤な合併症の予防」「生命予後の改善」です。そのために以下の層的アプローチが行われます。
【生活習慣・リスク因子修正】
禁煙(心血管疾患リスクを有意に低下させる)、規則的な有酸素運動(例:週150分程度の中強度運動)、体重管理(BMI 25未満を目安)、食事(飽和脂肪酸・トランス脂肪酸の制限、野菜・魚中心、塩分・糖分の適正化)、飲酒制限(適量以下)、ストレス管理・睡眠改善、寒冷・強い感情ストレス・重労作など発作誘因の回避策を講じます。
【薬物療法】
・硝酸薬(発作時および予防的に使用)
・β遮断薬(労作性狭心症では第一選択となることが多く、心拍数・血圧低下により心筋酸素需要を減少させます)
・カルシウム拮抗薬(特に冠攣縮性では有効)
・抗血小板薬(アスピリンなど。ステント留置後はデュアル抗血小板療法を数か月行います)
・脂質低下薬(スタチン等。動脈硬化進展抑制目的)
・ACE阻害薬/ARB(高血圧・糖尿病・腎疾患合併例には心血管保護も兼ねて使用)
医師が個々の患者背景・解剖学的・機能的血管評価をもとに薬剤を組み合わせます。
【血行再建療法】
薬物療法や生活習慣改善で十分な症状改善が得られない場合、また左主幹部病変・多枝病変・心機能低下・高リスク解剖といった予後改善が期待される場合には、冠動脈形成術(PCI)や冠動脈バイパス術(CABG)を検討します。再建適応は造影所見・FFR/iFR・患者全身状態・予後因子を総合判断します。
【急性発作時の応急対応】
発作時にはまず安静・座位あるいは半座位で安定を図り、すでに処方されている場合はニトログリセリン舌下またはスプレーを用います(1回吐かずに改善しない場合は5分以上経過後もう1回、改善なければ救急受診)。発作が15分以上持続する、冷や汗・嘔気・左肩・腕へ痛みが放散する、意識消失傾向があるなどの場合は、速やかに「119番」などの緊急搬送を要検討します。発作頻度増加・安静時発作・既存治療で抑えられない場合は不安定狭心症として緊急治療の対象となります。
【定期フォロー・予後管理】
定期的な外来受診・血圧・脂質・糖代謝・腎機能・喫煙状況のモニタリング、定期心電図・心エコー・血流予備能検査、再発リスクや合併症(心筋梗塞・心不全)の兆候チェックが重要です。特にステント留置後は再狭窄・血栓リスク、薬の継続・副作用チェックが必要です。
東中野周辺で狭心症が気になる方へ

胸の締めつけ感・動悸・息切れなど、「もしかして心臓が…?」と感じた症状がある場合、 狭心症が疑われます。心臓を動かすための血管(冠動脈)が細くなったり、 痙攣したりすることで起こるもので、適切な検査・治療が重要です。 この記事では検査方法・治療選択・受診の目安を東中野のクリニック視点で 分かりやすく解説しています。
記事を読む-
その他の呼吸器内科の病気
いたや内科クリニックの診療科一覧
-
循環器内科
狭心症、心筋梗塞、不整脈といった心臓に関連する病気に対応するのが循環器内科ですが、近年は高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などに由来する体全身の血管の動脈硬化に対応するようになっています。当院では日本循環器学会認定循環器内科専門医が診療にあたっております。
-
糖尿病内科
体内でのインスリンの枯渇や感受性の低下などによって血液中の血糖値が高くなってしまうのが糖尿病です。動脈硬化の強い因子と考えられており脳梗塞、心筋梗塞の原因となってしまいます。食事生活指導から内服治療、インスリン注射療法まで糖尿病治療全般に対応しております。糖尿病治療の重要な指標となる血糖、HbA1c値については院内で迅速で結果閲覧が可能です。
-

睡眠時無呼吸症候群
夜間睡眠中に呼吸が止まったり低下してしまう病気を睡眠時無呼吸症候群と言います。 睡眠疾患の代表格です。 呼吸の低下により睡眠の質は低下し、昼間眠いなどの直接的な症状の他に動脈硬化などの原因となることが証明されています。 原因である肥満などに対しての生活指導、内服薬に加えて空気圧で気道を広げるCPAPと言われる機械が使用されます。 軽症から重症まで病態は様々ですので患者様がどのような状態なのかを的確に判断し総合的な治療が必要となります。 当院では患者様のお話を聞き診察をさせて頂いたうえで、簡易検査から最終的な検査であるポリソムノグラフィーまで施行させていただき、必要であればCPAP治療まで行うことが可能です。歯科との連携による口腔内装置のご紹介も行っております。
-

生活習慣病
肥満を主な契機として全身の血管が狭く硬くなる病態を生活習慣病といいます。代表的な病気としては高血圧、糖尿病、高コレステロール血症があげられます。サイレントキラーと言われるように症状がないことが多いのですがゆっくり進行し将来的は狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などを起こします。 生活指導に加えて必要であれば内服薬の早期介入も必要です。当院では動脈硬化の専門家である循環器内科医が総合的なアプローチを行っております。
-

予防接種
現在小児へのワクチン対応は行っておりませんので、診察をご検討の方はご注意ください。 診察をご希望の方は、お電話にてご相談ください。
-

自費診療
ニンニク注射、AGA治療など対応しております
-
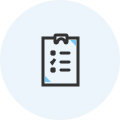
健康診断
現在患者の方がお受けできる健康診断の内容を確認中です。 準備ができ次第公開していきます。
-
呼吸器内科
咳や痰、息切れ、胸の違和感など、呼吸に関わる症状を専門的に診療するのが呼吸器内科です。気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺炎、間質性肺炎など幅広い疾患に対応します。呼吸機能の低下は日常生活の質を大きく左右するだけでなく、重症化すると全身状態にも影響を及ぼします。 原因となる喫煙やアレルギー、感染症などを評価し、生活指導や内服治療、吸入療法を組み合わせながら症状の改善を目指します。必要に応じて在宅酸素療法や専門的治療の導入も検討します。 症状の程度や経過は患者様ごとに異なるため、丁寧な問診と診察に加え、レントゲン検査やCT検査、呼吸機能検査、血液検査などを行い、総合的に診断いたします。当院では一人ひとりの状態に応じた継続的な管理と治療を行い、安心して日常生活を送っていただけるようサポートしております。
-
消化器内科
食道・胃・腸・肝臓・胆のう・膵臓など、消化に関わる臓器の病気を診療するのが消化器内科です。腹痛や胃もたれ、胸やけ、下痢や便秘、血便などの症状はもちろん、健康診断での異常値の精査も行います。消化器疾患は生活習慣と密接に関わっており、放置することで重篤な病気へ進行することもあります。 原因となる食生活や飲酒、ストレスなどに対する生活指導、内服治療に加え、必要に応じて内視鏡検査や超音波検査、CT検査などを実施します。早期発見・早期治療が重要であり、症状の背景を丁寧に評価することが大切です。 軽症から慢性疾患、悪性疾患まで病態は多岐にわたるため、患者様お一人おひとりの状態を的確に判断し、総合的な診療を行います。当院では問診と診察を丁寧に行ったうえで、胃カメラや大腸カメラなどの専門的検査にも対応し、継続的な治療とフォローアップを行っております。
-

往診応需
通院が困難な患者様のもとへ医師が伺い診療を行うことを往診と言います。ご高齢の方やお身体が不自由な方、急な体調不良で来院が難しい方などに対して、ご自宅で必要な医療を受けていただくための大切な診療形態です。病状によっては早期の対応が重症化の予防につながることもあります。 診察のうえで、症状に応じた内服治療や処置を行い、必要に応じて検査や専門医療機関へのご紹介も検討いたします。患者様の生活環境や介護状況も踏まえながら、無理のない治療方針を立てることが重要です。 当院では患者様やご家族のお話を丁寧に伺い、状況に応じて往診を行っております。症状の経過や全身状態を総合的に判断し、継続的なフォローが必要な場合には今後の診療方針についてもご相談させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
-
内科
どの科を受診したらわからない場合やどこの病院に診てもらえばいいかわからない場合もご相談ください。他の専門医に紹介が必要な場合は適切な科に紹介致します。


 クリニック紹介
クリニック紹介
 診療のご案内
診療のご案内
 いたや内科クリニックブログ
いたや内科クリニックブログ

